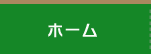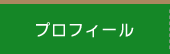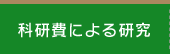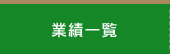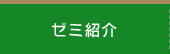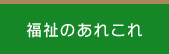福祉のあれこれ
ゼミ生と映画『STILL LIFE』を観て
2016.9.27
春学期のはじめ、ゼミの時間に学生たちと映画(DVD)を観た。ウベルト・パゾリーニ監督によるイギリス・イタリア合作の『STILL LIFE』、日本では『おみおくりの作法』というタイトルで2015年に公開された。
ロンドン市ケニントン地区のジョン・メイというclient services(民生係)の公務員が、いわゆる「孤独死」となった人々の死後事務を担い、葬儀まで行っていくというストーリーである。おそらく誰も進んでやりたがらないような仕事を淡々と、しかし誠実に、愛情をもってこなしていくジョン・メイ‥ 次第にその姿に引きずり込まれてしまう。そして、向かいのアパートに住んでいた人の孤独死ケースに直面したことで、彼の人生は一気に新たな展開を見せ始める。
日本でも孤独死の問題は、無縁社会というキーワードともに取り上げられるようになって久しい。誰にも看取られずひっそり亡くなっていく人の数は年間3万人以上に上るという。身近でないように見えて、とても身近な問題、しかしあまり突っ込んで考えたくない問題だろう。家族・地域・会社など従来の縁が築きにくくなったといわれる現在、社会福祉の視点から孤独死問題についてどのようなアプローチができるのだろうか。
『STILL LIFE』は、墓地や葬儀シーンから始まる地味な映画なので、若い学生たちがどう受け止めるか、正直心配だった。しかし、ストーリーが進むにつれ、映画に集中し観入っている雰囲気、熱気といってもいいような雰囲気を感じた。ラストに近づくシーンでは思わず声を上げる学生も…。今回私は学生たちといっしょに見て、これは死を扱った映画ではなく、ひとりの男性が自分の殻を破り、新たな人生を踏み出す物語でもあると思った。細部にまでこだわり、さまざまなことを考えさせてくれる実によく出来た映画である。
以下に、ゼミ生の書いた感想文を一部載せる。
この映画の存在は知っていて、観たいと思いながらなかなか観られていなかった。すごく考えさせられる映画であり、軽い気持ちでは観られないと思っていたからだ。今回ゼミで観る機会をいただき、自分の周りにもジョン・メイや彼に送られたような方たちが沢山存在するだろうと、自分に関係ないことではなく、いつ私がそのような状況に置かれてもおかしくないのだろうと思った。
特に印象に残った場面は、冒頭で独り暮らしのおばあさんが亡くなり、家の中にあるものからおばあさんの暮らしぶりを探る場面、亡くなった方の身寄りをようやく探し当てても葬式にさえ参列してもらえない場面など、、、(中略)ジョン・メイが、親族との関係が希薄になった故人の人生をたどっていくことは容易ではないようだった。
しかし、私はジョン・メイが遺品などから故人の人生を想像し、送り出す言葉を心を込めて考えることは意味のないことだとは思わなかった。たとえ独り身であっても、だれか一人だけでいいから、自分の死を悼み、歩んできた人生に思いを馳せてくれる人がほしいと考えるのはおかしくないと思う。(中略)現実の世界を見ても、独居の高齢者は増えており、親族とのつながりが希薄な方も多い。無縁仏となる方も多いようだ。そうなる前にどこかで繋がりを回復できる機会があればという思いと、亡くなった時にその死を悼む人や場は必要であるという思いが私にはある。(3年 A.K.)
人生のゴールである死を、誰にも知られず、一人で迎え、その後面会や遺体引き取り、葬式なども拒否されてしまうなんて、あまりに寂しくて、やり切れないと思った。「理想の死」を迎えることはとても難しいことだが、自分の死を悲しんでくれる人が一人もいないという最期は、人生に正解・不正解はないにしても、とても胸を張れるものではない。そして、こうした最期を迎える方が現実に大勢いて問題になっているということは異常事態だ。(中略)
看取り屋(?)という職業をこの映画ではじめて知った。孤独死に陥った方の身辺を調査し、身内を探し、連絡を取るという職業なのだと思うが、そういった仕事は警察がやるものだと思っていた。映画の主人公は仕事に誇りを持っていて、死者のために尽くそうとしている様子が見られたが、そんな主人公とは対照的に、死者の家族は無関心で、上司は効率を重視する。その対比が、余計にやりきれなさを感じさせた。教会や墓地で一人主人公が立つシーンには、こんなに人の最期はあっけなく味気ないものであっていいのか、と思わされ胸を打たれた。(3年 K.U.)
全体的な感想としては、最初の方は何だか暗い映画だなと思っていたが、観ていくうちに主人公の人柄や仕事に対する熱意に惹かれていき、最後のシーンではグッとくるものがあった。印象に残ったのは、主人公の上司の「死者の想いは存在しない。残された者も死者の葬儀や状態について知りたいと思わない」というセリフである。主人公は亡くなった人をきちんと葬儀してあげたいと考えているが、上司は弔う人がいないなら葬儀は無意味であると考えていたのである。そのセリフを聞いたとき、私は上司の考えに一理あるのではないかと思った。しかしながら、その後で亡くなった人の娘が「ありがとう、伝えてくれて」と主人公に感謝するシーンがあり、残された者も最初は葬儀など知りたくないと思ったとしても、何かしらのきっかけがあればそのように心もほぐれていくのではないかと思った。生きている人にせよ亡くなった人にせよ、一人の人を知るためには多くの時間や手間がかかってしまうのだと改めて思った。(4年 M.H.)
映画の中で一番印象に残ったのは、主人公が故人のために弔辞を書いているシーンだ。主人公が一人ひとり丁寧に考えて書いているのが分かった。故人の残した写真や手紙などを参考に、心からの弔辞を書いているシーンにとても興味を持った。弔辞を書くために参考にする遺留品もかなり凝った作りで、実際に生きていた人の過去を振り返っているように感じられた。家族がいなかったとしても、その人が生きてきた軌跡は消えることがない。孤独死をテーマにした映画だが、登場人物を丁寧に扱っていることで、より映画に重みが出ているのではないだろうか。職業として多くの人の死や生に携わっていると、あってはならないことだが、人の個別性に目を向けることが少なくなってくると思う。この映画は、人として大切なことを改めて認識させてくれる力を持っているのではないかと思った。(4年 Y.N.)