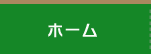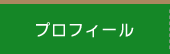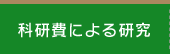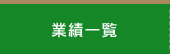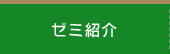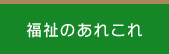福祉のあれこれ
アウシュヴィッツが語りかけるもの
2019.10.10
9月初旬に1週間ほどポーランドを訪れる機会を得た。目的の1つはアウシュヴィッツ・ミュージアムに行くこと、そこでガイドを務める中谷剛さんの説明を聴くことだった。中谷さんとの出会いは2年前にさかのぼる。TBSラジオに出ていた中谷さんがガイドとして伝えることの意味や、「過去を知ることで現在の立ち位置が見えてきて、これからの方向― 何を選択するのか、選択しないのかがわかる」といったことを語っていた。偶然耳にした番組で、アウシュヴィッツでの唯一の日本人公式ガイドという点にまず興味をそそられた。私自身ちょうど「伝える」ことの意味について考えていたときでもあった。私の研究テーマとも重なり、いつか中谷さんのガイドでアウシュヴィッツ・ミュージアムを歩いてみたいと強く望むようになった。
その願いがかなったのが9月6日午後2時、夏を思わせる陽ざしが降り注ぐ日だった。アウシュヴィッツ・ミュージアムのインフォメーション・センターの前には大型バスが何台も駐車していて、一大観光地のようだった。中谷さんは入口付近で私を含む日本人参観者を待っていた。当日の日本人グループは総勢30数名、年齢層は幅広く男女はほぼ同じ割合といった構成だった(残念ながら参観者間で話す時間はほとんどなく、互いの参観動機などはわからなかった)。入口で荷物チェックを受けた後、中谷さんのガイドを聞き取るためのヘッドホンを借りる。
まず、あの有名な「ALBEIT MACHT FREI(働けば自由になる)」の文字を掲げるゲートを通る。思ったより小さかった。広い敷地にはれんが造りの頑丈な建物(収容棟)が整然と並ぶ。脇にはポプラ並木… 青空が広がっていたせいか、大学のキャンパスのような印象だ。ところが建物の中に入るとそうはいかない。石の階段、狭い廊下を進むと、展示室の壁には当時の収容棟、着いたばかりで「(生死の)選別」を待つユダヤ人の姿などを映した写真が展示されている。ガス室・焼却炉の建物の模型もある。中谷さんは抑えたトーンで展示物の説明をしながら、なぜユダヤ人の迫害が始まったのか、ユダヤ人の定義とは、文化度が高く多数のノーベル受賞者を輩出してきたドイツがなぜこうした虐殺行為に走ったのかなど、当時の政治・社会状況を踏まえて語っていく。
展示の中で圧巻なのは毛髪のおびただしい山に、眼鏡、靴、車いすや杖などの山。食器など日用品の山もある。幼児の可愛らしい服や靴がきちんとガラスケースに収まっている。写真集などで見たことがある光景だが、ガラス越しに直に見るこうした遺留品は圧倒的な衝撃で迫ってくる。ポーランド人の抵抗活動家の「処刑」場となった「死の壁」も通る。多くの参観者グループと行き交ったが、みな無言のままだった。
参観の中盤で中谷さんは「今までヒトラーの写真が1枚もなかったことに気づいたでしょうか」と問いかけた。確かに、あの独特な姿の写真はどこにもなかった。このミュージアムがヒトラーやナチスの蛮行を非難するためのものではないことを表している。私はここに来るまで、ホロコーストは一人の狂気に満ちた人間とその命令に服従した部下たちの存在が大きいと思っていた。しかし中谷さんは、当時の社会状況を振り返りナチ党は国民の大多数の支持を得ていたわけではなく、むしろ大衆の迎合主義や政治への無関心がヒトラーへの全権委任の道を開いたことを指摘する。そして、そうした無関心は現代にも通じて存在すること、今のヘイトスピーチの先には何があるか、共生社会とはどういう社会の在り方なのか等々、みなが考えることの必要性を強調した。中谷さんの話は一貫して現代社会に結び付けた内容だった。
休憩をはさんで後半はもう1つの収容所ビルケナウにバスで向かった。約3キロ北方にあるビルケナウはアウシュヴィッツよりもはるかに広い。アンネ・フランクが一時期収容されていたことでも知られる。やや西に傾きかけた陽ざしが平地を広くおおっている。
「死の門」と呼ばれる大きなゲートとそこ通る長い鉄道引き込み線、映画の一場面を見ているようだった。窓のない家畜用貨車で何十万人というユダヤ人が移送され、再び出ることなく命を奪われた「絶滅収容所」―中谷さんはガス室までの道のりを歩きながら、当時どのようにユダヤ人が「選別」されガス室まで歩かされていったか、その様子を詳しく語った。ガス室と焼却炉を兼ねたクレマトリウムは無残な残骸となっている。収容所の解放間近に、証拠隠滅のためナチス親衛隊(SS)によって爆破されたという。中谷さんの説明がなければどこが入口、階段でガス室に通じていたのかわからない。何か異様な、巨大なコンクリートの残骸物があるといった感じだった。
木造の収容棟は老朽化が進んでおり、中まで入れる収容棟は限られていた。ビルケナウのような広大な収容所跡を維持保存するのはさぞ大変だろうと思ったが、中谷さんによれば維持経費はドイツ政府がかなり負担しているそうだ。ドイツの歴史認識の重さを感じる。
約3時間あまり、中谷さんのガイド付きの参観は終わった。沢山歩き、多くのものを見て感じ考え、あっという間の時間だった。中谷さんがラジオで「事実だけを伝えるのではなく、ガイドとしての気持ち、どういう社会になってほしいかを乗せていく」と語っていたことが会得できた時間でもあった。歴史的遺物を展示しそれらをただ眺めるだけなら、「博物館」にしか過ぎない。70数年経た今もこうして残しておく意味、私たちが直に触れる意味、現代的意味について考えなくてはならないだろう。
今回ポーランドを訪れるにあたって、にわか勉強ながらホロコーストやアウシュヴィッツ、ポーランドに関する本を読み漁った。中でも、プリーモ・レーヴィ著『これが人間か―アウシュヴィッツは終わらない』(竹山博英訳 朝日新聞出版)が印象に残った。プリーモ・レーヴィはイタリア系ユダヤ人で、レジスタンス運動に加わっていたため1944年2月アウシュヴィッツ収容所に送られ45年1月まで抑留された。奇跡的に生還し、地獄のような収容所生活、人間の魂の極限状態を克明に綴ったのが同書である。
現在私は、苛烈な体験をした人の体験への意味づけに関心をもっているが、レーヴィの本からとくに示唆的だった文章を以下に記す。
(1973年刊『これが人間か』学生版の「若い読者に答える」という形で末尾に収録されている文章から。)
「全体的に見るなら、この過去は私を豊かで、確かな人間にしてくれた。…… つまりあの出来事を生き抜き、後に考え、書くことで、私は人間と世界について多くのことを学んだのだ。
しかしこうした前向きの結果はわずかな人にしか訪れなかったことを、すぐに付け加えておこう。…… おそらく、人間の魂への関心を決して絶やさなかったことや、単に生きのびるだけでなく、体験し、耐え忍んだことを語るために生きのびるのだ、というはっきりした意志を持っていたことが、私を助けてくれたのだろう。…… 」