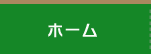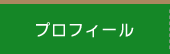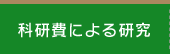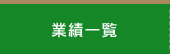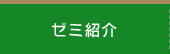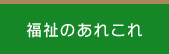福祉のあれこれ
2024年度(2024年4月~2025年3月)を振り返って 被害者支援のさらなる進展に向けて
2025.5.29
2024年度も被害者支援のさらなる進展に向けて邁進した1年となった。特筆すべきことの1つは、科研費による研究成果をまとめた本を刊行できたこと。またこの1年は、被害者支援にかかわる研修や法務省の視察などで沖縄、北海道、宮崎、高知など日本各地、そしてバンクーバーまで訪れることができ、美しい景色とともに忘れがたい想い出に彩られた年となった。
4月 警察庁「地方における途切れない支援の提供体制の強化」検討会の取りまとめを終えて
政府の要請を受けて昨年秋から本格的に動き出した「地方における途切れない支援の提供体制の強化」について、有識者検討会の結果がまとめられた。私はこの検討会の座長としてかかわったが、まず全国の地方公共団体を対象にしたアンケート調査を実施し、支援現場の実情を知るためにヒアリング調査を実施した。ヒアリング調査に同行し、全国10数か所の自治体、警察、民間支援団体の担当職員の生の声を聴いた(全体では51か所にヒアリング調査を実施)。さまざまな被害者支援の現場を直接把握できた貴重な機会だった。
それら調査結果と8回に及ぶ検討会での討議を踏まえて、2024年4月に「取りまとめ」が提出された。都道府県を中心としたワンストップサービス体制を構築し、市区町村、民間支援団体等の関係機関・団体との連携を強化することを提言した具体的な内容となっている。地域間の格差をなくし、必要な制度や支援サービスが犯罪被害にあった人々のもとに確実に届くことを目指している。
「取りまとめ」は6月に犯罪被害者等施策推進会議において了承・公表され、「概要版」と「全文」が以下のURLに載っている。
https://www.npa.go.jp/hanzaihigai/meeting/local_kyouka/kaisai/
この「取りまとめ」を具現化するために、「手引き」を作り、オンライン研修も実施することになっている。ワンストップサービス体制の要となるコーディネーターの育成や関係機関の連携のための意識向上など課題は多いが、「取りまとめ」で提言した取組が全国に浸透していくことを願っている。
余談になるが、5月下旬にはこの検討会を担った警察庁犯罪被害者等施策推進課のみなさんと打ち上げの機会をもった。警察庁の方をはじめ全国の道府県警察から派遣された警察官とともに取り組んだ仕事、全国行脚の日々、忙しくもあり、楽しくもあり… 私自身のキャリアは警視庁の心理職から始まったので、今回の仕事はとくに感慨深いものとなった。
6月 拙編著「犯罪被害と『回復』 求められる支援」を刊行!
6月にようやく、科学研究費助成事業による「『被害からの回復』に関する犯罪被害者調査」の一環として実施したインタビュー調査をまとめた本を刊行した(本ホームページのトッピク参照)。調査を実施したときから、その結果を書籍という形で残したいと考えていたが、研究分担者からはよい反応を得られず、刊行してくれる出版社のあてもなく前途多難だった。
しかし、犯罪被害者の実情を広く知ってもらいたい、被害者の側にたった支援体制を推し進めたいという一念で、何とか刊行にこぎつけることができた。何よりインタビューに快く応じて下さった当事者22名の方々、支援する側の声やコラムを執筆いただいたみなさんに感謝している。小さな本だが、一人でも多くの方の手に取っていただくことがあれば幸いである。
6月 沖縄へ 日本被害者学会学術大会に参加
6月29日琉球大学千原キャンパスで日本被害者学会の第34回学術大会が開催された。コロナ禍以降はじめての地方での開催であった。
シンポジウムのテーマは「地域における被害者支援のあり方―沖縄で被害者に寄り添う人々―」で、沖縄という地域性を踏まえた興味深い報告が続いた。やはり基地問題に絡む犯罪被害の問題が根深く、地道に被害者支援に取り組んでおられる方々、とくに女性の支援者や研究者の姿が印象に残った。
私にとっては久しぶりの沖縄訪問、今回は南部の平和記念公園、ひめゆりの塔まで足を延ばすことができた。また、大学時代の友人が千葉県から移住して沖縄県中頭郡にある中城村に保育園を開いたこともあって、その可愛い保育園を訪問したり、中城城跡、識名園や旧海軍司令部壕を案内してもらったりした。沖縄の歴史に深く触れる充実した旅となった。持つべきものは古き良き友だち!である。
10月 法務省の視察で北海道・旭川と網走へ
10月10~11日、秋晴れの穏やかな天候のもと法務省の仕事の視察で北海道を訪れた。視察先は旭川保護観察所、更生保護施設旭川清和荘、旭川更生保護協会、網走刑務所、網走監獄博物館、網走駐在官事務所。印象的だったのは、旭川で薬物問題に苦しむ人たちが集まるミーティングに参加できたこと。「『やめられないこころ』に負けないように、つながろう、支え合おう」をテーマに、当事者たちが集まり日頃の生活や思いを語り合う。そのゆるやかな雰囲気にリカバリーのヒントをもらったような気がした。
また、網走刑務所では二見ケ岡農場に足を運び、北海道ならではの矯正のあり方を垣間見ることができた。網走監獄博物館も現在北海道で2番目に人気の観光スポットというだけあって、重要文化財の木造建築はもちろん、全体になかなか見応えがあった。百数十年前の監獄、その囚人たちが道央とオホーツク沿岸を結ぶ道路の開拓工事に駆り出された歴史を知り衝撃を受けた。一度は訪れてみる価値のある博物館だと感じる。
11月 宮崎の被害者支援のための会議に招かれて
11月7日、「日本のひなた宮崎県」というキャッチフレーズの明るい南国で開催された、令和6年度「宮崎県・市町村犯罪被害者等施策主管課長会議」に招かれて講演を行った。テーマは「自治体における犯罪被害者等支援のあり方―被害者の声をもとに考える」。参加者は同県内の市町村担当職員、県警察本部職員、みやざき被害者支援センター職員、県関係課職員等で、オンライン参加者も含め熱心に参加していただいた。
宮崎県の犯罪被害者等支援条例の制定状況は、県が令和3年7月に制定、26市町村のうち12市町村がすでに制定し、8市町村が令和7年度までに制定する予定となっている。市町村での支援メニューとしては、見舞金、公営住宅の優先入居、相談対応等を用意しているが、多くの市町村で犯罪被害の相談がない状況とのこと。犯罪件数が少ないのは好ましいが、被害にあっても役所の支援を知らなかったり、制度に結びつかなかったりするような場合はないだろうか。被害者支援に前向きな職員の方が多かっただけに、アウトリーチの手法を取り入れるなど自ら出向いて被害者に支援を届ける方策を工夫してほしい。
12月 渋谷区の映画祭トークセッションに招かれて
12月14日渋谷インクルーシブシティセンター<アイリス>が主催する映画祭のトークセッションに招かれた。この<アイリス>は「ジェンダーやセクシュアリティなど、人権を尊重し差別をなくす社会を推進するための学習・活動・交流および情報提供の拠点となる施設」(HPより)で、毎年ジェンダーや人権などを扱った映画上映&トークセッションを開催している。
今年のテーマは「関わること、対話すること、聴(ゆる)すこと」で、『カラーパープル』『ザ・ホエール』『ぼくたちの哲学教室』など5本の映画が取り上げられた。私はそのうちの『対峙』という映画のトークセッションに出る機会を得た。『対峙』は2021年アメリカ制作(脚本・監督:フラン・クランツ)で、高校銃乱射事件で双方とも息子を失った被害者と加害者の両親が向き合い、言葉を交わしていく緊迫したドラマ映画である。修復的司法を扱っているともいわれ、日本で公開されてすぐに観たがその臨場感に圧倒された。
『対峙』のトークセッションでの相手はドキュメンタリー映画監督の坂上香さん。坂上さんは映像作家として加害者の更生に関わってきている立場からコメントされた。私は、このような被害者側と加害者側の対話が日本でも成り立ちうるのか、その対話がもつパワーなどについて話した。日本の更生保護や矯正の分野で実施されている「心情等聴取・伝達制度」についても言及した。
時間が限られていたので十分には話せなかったが、被害、加害を経験した者の心情、癒しなど思いを巡らすきっかけになればうれしく思う。また、スタッフのみなさんは好感が持てる方ばかりで、渋谷区が<アイリス>のような施設を運営し、さまざまなイベントや情報提供を行っているのは大変心強いことだと感心した。
2025年1月 高知の被害者支援に係る研修会に参加
1月15日、高知県で開催された、被害者支援に係る関係機関向けの研修会に参加した。これは警察庁が2024年6月に公表した「地方における途切れない支援の提供体制の強化」の取りまとめを広く理解してもらい定着させるために、全国で実施している研修会の1つである。
参加者は自治体をはじめ、司法、教育、民間支援団体等の支援担当者で、想定事例に基づくシミュレーション訓練やインテーク面接のロールプレイなどを3時間にわたって実施した。全体を振り返っての討議も実に活発で、さまざまな現場で被害者支援に携わる者の意識が高まっていることを実感した。研修会を通して、関係機関の連携が強まりワンストップサービス体制が整備されていくことを願っている。
2月 法務省保護局の視察でカナダ・ブリティッシュコロンビアへ
2月25日から約1週間、法務省保護局の視察に同行してカナダ・ブリティッシュコロンビアを訪れた。視察の目的は、カナダ矯正局、更生保護・被害者支援を担う機関、修復的司法を実践する非営利活動法人等の現場を訪れ、日本の制度と比較・検討を行うことであった。視察先ではどこも温かく迎えてくださり、惜しみなく情報提供していただいた。
とくに印象的だったこと2点をあげたい。1点目はバンクーバー市警察の被害者支援室の活動。支援室のマネージャーはソーシャルワーカーであり、20数名のスタッフ(非常勤を含む)とともに、被害直後から被害者に寄り添って、安全確保、精神的・実用的なサポート、ニーズアセスメント、情報提供など適切なサービスを広範囲に実施していた。ソーシャルワークの視点が随所に感じられた。
2点目は、犯罪学者のDavid Gustafson氏が主催するCommunity Justice Initiativeを通して、修復的対話を経験した被害者遺族の方2名、加害者青年2名から話を伺うことができたこと。被害者にとって、加害者のありのままの姿を見て直接ことばを聴くことは、自らパワーを得ることや心の癒しにつながることがよく分かった。また一方、加害者にとって真の反省や謝罪に至るには、周囲のサポートが必要であり、自分のことを理解しサポートしてくれる人がいてはじめて、被害者のことを考える心のスペースができるのではないかと感じた。
このカナダ視察については、2025年度に何らかの形で報告としてまとめる予定である。