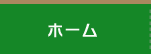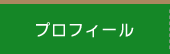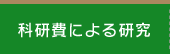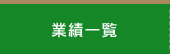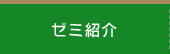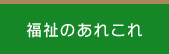ゼミ紹介
ゼミ生の参観レポート
ダイアログ・イン・ザ・ダークを経験して
2017年度春学期の演習のテーマは「対話」とした。対話と聞いて何を思い浮かべるだろうか。「圧力の強化より対話の努力を」、「対話による解決」、「対話型の学習プログラム」など‥ 最近は対話ということばをさまざまな場面でよく聞くようになった。
私は修復的司法における対話に関心をもっている。学生たちと対話について多角的に考えてみたいと思い、今期このテーマを選んだ。使用したテキストは、暉峻 淑子著(2017)『対話する社会へ 』(岩波新書) 。テキストをもとにグループでプレゼンするとともに、フィールドワークも2か所で行った。1か所目は、ダイアログ・イン・ザ・ダーク(DID)への参加である。
DIDは「暗闇のソーシャルエンターテインメント」を謳い、真っ暗な空間へ視覚障がい者のアテンドで、グループで入っていき、さまざまなシーンを体験するというもの。1988年ドイツで始まり、これまで世界41カ国以上で開催されているという。日本では1999年に初開催、現在東京と大阪(「対話のある家」がテーマ)を中心に開催されており、これまで20万人以上が体験しているとのこと。
暗闇でどんなダイアログ(対話)が展開されるのだろうと、私自身かねてからDIDに興味があった。今回ゼミの課題として、各自が申込んで参加することとした。
私は5月23日神宮前会場のDIDに参加した。実に「濃い」ピュアな90分間、人って信頼できるんだ、信頼していいんだという心地よさを味わった。一言でいうのなら、すがすがしい体験だった。見えるという情報が、かえって人との関係を疎遠にしているのではないかと気づいた体験でもあった。そのあたりについては学生たちも同様な感想をもっているので、詳しくは以下学生たちの感想レポートを読んでいただきたい。
3年 M.T.
「ダイアログ・イン・ザ・ダーク(DID)」は視覚障害者の案内のもと暗闇の中を探索するというもので、私は他のゼミ生3人と一緒に参加し光の遮断された空間で視覚以外の感覚の可能性と対話を体験することができた。
暗闇という何も見えない空間で頼りになるのは音だった。暗闇の中では身振り手振りが一切伝わらないため、相手の言葉に反応する時やリアクションは全て声を通じて伝えなくてはならなかった。私たちは日常的に同調の気持ちを示す際頷きによって言葉で伝えることを省略している。しかし暗闇では頷きは相手に伝わらない。自分の言葉に対して相手はどう感じたのか、どのような意見を持っているのかをはっきりと自分の言葉で伝えていく必要がある面白さは日常では体験できないものだった。同調の気持ちの示し方は様々で「なるほど」「そうだよね」といった言葉だけでなくそこに付け加えてその人の言葉が足されることで会話は徐々に対話へと変化していくことが分かった。疑問に思うことは首を傾げていても伝わらないため積極的に質問していく必要がありこれもまた対話をする上で重要なプロセスである。また相手の言葉を心に留めておく難しさを感じた。私は人の話を聞いて感動したことや覚えておきたいことをメモする癖があるが見えない世界ではメモは何の役にも立たない。相手の言葉一つ一つを大切に真摯に向き合うことで、その瞬間対話は成立すると感じた。
私はDIDに参加して、見えない相手と声という手段を頼りにコミュニケーションを取ることで見える時よりも自分の意見や考えを本音で伝え相手の本音にも真剣に向き合うことができたと感じた。これは普段の生活では味わえない充実感があり、普段見えているものは見えないが普段見えないものが見えてくるような感覚を感じることができた。視覚障害者のガイドの方が話していた「目が見えなくなって人を信じようと思うようになった」という言葉は印象的であったが、見えない世界を体験して初めてその感覚を理解した。見えない世界では隣にいる人の言葉を信じて前に進むしかなく人の力を借りる必要があった。参加者8人は初対面の人が半数だったが、暗闇の中でお互いを信じ合い本音で対話をすることで安心感や信頼が生まれた。このことから対話は相手を信じて初めて成立するものであり、同調も反対の意思も自分の言葉で伝えようとすることで充実したものになると感じた。
3年 M.F.
私は体験する前までは、暗闇の中で会話をするという非日常のことを考えるだけで、好奇心よりも不安感が募っていた。さらに、一緒に体験するとわかったのが自分よりもはるかに年上に見える4人の男の人たち。正直早く終わらせて女子4人で帰りたいという思いが強かった。暗闇のエキスパートと呼ばれる盲目のロッキーが案内をしてくれて純度100%の想像以上の真っ暗闇の中に入ったとき、私の不安は最高潮に達した。不安でいっぱいになりながらも、ロッキーの呼ぶ方に白杖を使って参加者で声を掛け合いながら進んだ。「こっちだよー」「ここ段差みたいなのがあるから気を付けてね」初めて会った人たちでも、相手のことを信頼し、飲み物や食べ物もにおいや感触などの目以外の感覚を研ぎ澄ますという新たな挑戦は、馴染みのある食べものでもなぜかとてもおいしく感じたのと同時に、いかに自分が視覚に頼り切っていたのかを思い知った。最後にみんなで席について薄暗い闇の中でフィードバックをした。見えることへの安心感があったが、見えたことで人と人とが切り分けられ、グループの一体感みたいなものが消え、孤独感のような不思議な気持ちになった。
ある男性が悪気はなかったのかもしれないが、「見えないって損だな」とこぼした。どうかロッキーには聞こえていないようにと思っていたが、彼の耳には届いており、傷ついたような雰囲気だった。「僕は突然目が見えなくなってしまったけど、見えていたときより見えない今の方がいい。見えていたときには見えなかったものが見えるし、見えないからこそいろんなことに挑戦したいと考えるようになる」というロッキーの話を聞いて、この人の方が私よりも世界が見えているのではないかという気がした。
私はこの体験を通して、人の温もり、声を掛け合うことがなにも見えなかった自分にとっていかに大切なのかを知った。そしてたった一本の棒(白杖)でも、叩くことで音の違いに気づき、ここが柔らかい地面なのか、固い地面なのか、物に当たりそうかどうか知ることができる、なくてはならない魔法の杖のようなものなのだと身をもって感じた。今まで、見たくてもどんなに頑張っても見えないという経験はもちろんなかったので、目が見えることが素晴らしいのだとかそういうことではなく、心の目で見ること、だれかのことを信頼してみること、人間同士のいかなる状況下でも支え合っていこうというその姿勢がなによりも大事で尊いことなのだと学んだ。暗闇の中では一人ではなく、むしろ自分と隔てるものがないからこそ見える感覚がある。私は自分に本来備わっている目以外の感覚をもっと大切にして、心の目をもっと研ぎ澄ませていきたいと感じている。このような体験をする機会に恵まれたことに感謝したい。
4年 A.K.
私は、東京のDIDに一人で参加した。まず、待ち時間の間に、友人と一緒に参加すればよかった、知り合いのいない中で暗闇体験するなんてとても怖いという気持ちが膨らんでいった。その気持ちは、暗闇に足を入れる前、白状選びとチームメンバーとの自己紹介の時まで続いていた。
しかし、薄暗い空間で自己紹介をした後、いよいよ真っ暗闇(光を完全に遮断した空間)に放り込まれた時、怖い気持ちだけでなくワクワクした気持ちが膨らんできた。
自分一人では一歩前に踏み出すことさえも怖いけれど、「〇〇さーん!」、「足元の段差に気をつけて」、「右手に、葉っぱがありますよ」と気付いたことを何でもメンバーと共有し、声を掛け合うことで、段々と不安感が薄まってくる。暗闇の中に入るまで、赤の他人だったメンバーが、私にとってとても大事な人になっていった。仲間の声や動きを察知するために自分の感覚を研ぎ澄まし、仲間と少しでも多くの情報を共有するために、視覚以外の触覚や嗅覚、味覚をフル活用した。
DIDを体験している中で思ったことがある。それは、「人ってあたたかいんだ」ということだ。進む方向がわからなくなった時、メンバーの一人が「○○さんですか?こっちですよ」と私の手に触れてくれた。仲間の優しい声色に安堵し、手が触れた瞬間に、(ああ、助かった)という気持ちになった。普段は、基本的になんでも一人でできる年齢になっているが、暗闇空間だと何もできない。だからこそ、人の温もりやコミュニケーションの大切さを強く感じることができるのだと学んだ。
最後に、印象に残っている言葉と私の考えを述べたい。暗闇のエキスパート(アテンドをして下さった視覚障害者の方)の「僕たちは、相手の顔や風貌が見えない。でも、それは可哀想なことではないと思っている。相手の声で恋をしたこともあるんだ。相手の優しさに気付きやすいと思う」という言葉を聞いた時に、はっとした。私は、目を使わないで他人のことを知ろうとした経験がない。視覚がOFFになった時、目以外の感覚を研ぎ澄まして相手と向き合うことで、今とは違う何かが見えてくるのかもしれないと思った。
DIDに参加して2ヶ月が経った。私は、必死に互いの感覚を共有し、人の温もりをたっぷりと感じられたこの経験を、同じ学部の人だけでなく、様々な世代の人に伝えている。今回は、一人で参加してよかったと思っている。次は、家族や友人、大切な人と一緒に参加してみたい。
4年 K.H.
私は大阪のDIDを経験した。テーマは「家、インテリア」で、暗闇の中にある家に入って、そのつくりやインテリアを、五感を使って感じるというものだった。
外での説明が終わり、真っ暗闇の一つ手前の部屋まで行くと、視覚障害をお持ちのスタッフの方が出迎えてくれた。視覚障害者が日頃使っている白杖(はくじょう)を手渡され、徐々に室内が暗転していき、完全な闇になると、その日初めて、心からの不安が押し寄せてくるのが自分でもわかった。初めは何をやるのかワクワクだった気持ちも、正直この時は、これからこんな何も見えない空間の中で自分はやっていけるのかという気持ちで支配されていった。
そんな不安な気持ちのまま、まず玄関まで歩くという指示が出たのだが、暗闇であるだけで全く前に進めなくなることにまず驚いた。自分のいる位置が全く分からないため進もうにしてもどうしたらいいか分からないからだ。そこで、説明の際に言われた一番大事なルールである、「常に声を出して自分が今何をしているか知らせること」を思い出し、実践してみた。すると、自然に年の差も関係なく、他の体験者との距離も近づき、あの人の言っていることは安心して信じられるという気持ちになり、お互いに声を掛け合って、だんだんとスムーズに移動していけるようになった。移動の中では、ウッドデッキに出てハンモックに揺られてみたり、ゴザの上に座ってお茶とお菓子を楽しんだりもした。最後に、体験者とスタッフで輪になって座って、置いてある様々な形のクッションを触りつつ、談話をする機会があったが、その時は、初めには考えられなかったほど、自分も含めみんな自然に会話が飛び出し、いい意味で何も考えずにそれを楽しんでいるようだった。その時に、ゼミで深堀りしてきた対話の定義である、「ありのままの本心、傾聴、受容」が自然に思い出されて、まさにそれが実践できているなと感じることができた。
DIDを体験してみて思ったことは、対話さえできればどんな環境でも、どんなに年齢が離れていても関係ないということだ。つまり、本当に今回のような真の対話ができれば、それこそ人種、宗教、性別、階層など関係なく、世界中どこでも人が人として心を通わせられることができるのではないか、と真剣に思った。