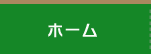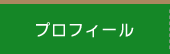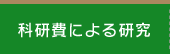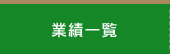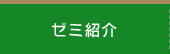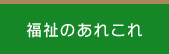ゼミ紹介
ゼミ生の参観レポート
対話の会を訪問して
2017年度春学期の演習のテーマは「対話」であった。ダイアログ・イン・ザ・ダークの参加に続いて、フィールドワーク2か所目としてNPO法人対話の会・東京支部を訪問した。対話の会は修復的司法の考え方に基づき、人間関係をめぐる学校・地域でのトラブルや犯罪をめぐる被害者と加害者の問題を、対話によって解決しようと実践している団体である。こうした修復的対話を実践しているところは、日本にはまだ少なく、対話の会は先駆的な貴重な実践を重ねているといえる。
当日は真夏の日差しが照りつける暑い日だったが、アイスクリームのもてなしを受け、この会を運営するスタッフの方々から対話の進め方などについて具体的な話を伺うことができた。以下、学生たちの感想レポートの一部を載せる。
3年 R.M.
私が対話の会を訪問して最初に感じたことは、スタッフはなんて穏やかな方々なのだろうということだった。初めての訪問、緊張した面持ちで伺ったのだが、とてもあたたかく常に笑顔で話してくださった。対話の会が被害者・加害者本人たちの意志を尊重する場所であるという点について述べたい。
私が対話の会は本人の意志を尊重する場である感じたのは、「対話の会を通して生活道路に空いた陥没した穴を、何とか通れる程度に穴を埋める」という言葉がとても印象的だったからだ。第三者である進行役が正しい穴の埋め方を説明し、その指示に当事者が従って“完全に整備された道”を作ることは可能だと思う。しかし、それでは本人たちの意志がそこにはない、つまり対話が成り立っていないからだ。自らが主体となり、自らの意志で解決方法を探ることが目的であり、完璧な道を作ることが対話の会のゴールではないことを学んだ。
また実例の中に、事前準備で加害者の少年と会う約束をしていたにもかかわらず、何時間も待ったのに結局来なかったというお話があった。来なかった少年に対して決して怒らなかったのは、本人の意志で参加することを重要視しているからだと知った。非行少年を相手にしていることもあり、それだけ進行役は彼らを受け入れる姿勢が必要だと思う。さらに加害者・被害者両者の心を開くには長い時間がかかると思った。実際に一つの案件を何年もかけて取り扱うとのことだったが、一つの事件に関わる一人一人に丁寧なアセスメントを行い、各々のニーズの把握をしているからだと感じた。
対話の会は解決を目的としておらず、加害者・被害者お互いのニーズを分かち合うことを目標としている。もちろんそのために当事者同士やその家族と対話を行うが、前提として進行役がそれぞれと対話を行い、信頼関係を構築することによって成り立っていると思った。
4年 M.M.
対話の会を訪問させていただいて、対話の会の目的は「問題解決することだけではなく、生活道路に空いた穴を他の人と一緒に土を盛って整えていく」と表現されていたことが最も印象的だった。お互いのニーズを引き出し、理解しそのうえで今後どうしていくのかを一緒に考えるために、事前準備を十分にしてから開かれることを知った。また、被害者が加害者に対して、「土下座をさせたい」「文句を言いたい」など攻撃的に加害者を責めたい場合は、2次被害となることもあるため直接会うことを保留するとのことだった。
段階として第1段階では私メッセージと呼ばれる表現で自分のことを話し、第2段階では質問に答え、第3段階ではこれからどうしていきたいのか話し合い、第4段階では文章にして約束事を書くという流れであることがわかった。第4段階の約束事を紙に書くという行為に関して、1つ事例を挙げられた。それはお墓参りに関してのことで、「約束事を紙に書いてしまうと約束だから来るということになってしまう」という被害者の遺族の方の言葉だった。確かに、紙に書いてしまえばそれは自主的なことではなく義務になってしまう。それは被害者の遺族の方が望んでいるものとは違うということである。加害者側の少年は「また自分が責められるのではないか」「こわい」という不安から約束の日に来ないなど、1件につき1年半から2年越しで抱える案件もあり、いかに信頼関係を築くことができるかということが重要になってくると思った。
対話の会を運営されている方々は弁護士や幼稚園の先生、不動産屋さんなど本当に様々な職業の方がいらっしゃり、地域で支えていることを感じると同時に、私達にとって遠い存在なのではなく、身近にあることなのだと思った。対話の会のことを私は今まで知らなかったのだが、まだまだ知らない人も多くいると思う。多くの方が知ることで1人でも多くの犯罪被害者・加害者がともに良い方向へ進むことが出来ればと考えた。
4年 K.U.
対話の会の存在を知って、また実際にお話をうかがって、その存在自体が司法福祉の希望を示していると思った。
対話の会は、被害者と加害者による話し合いの場であり、そこに法的拘束力はない。あくまで会は話し合い、理解の場であり、解決の場ではないからだ。依頼者の希望のもと、参加願いの手紙を相手に届け、そのやりとりを通して「行ってもいい」と相手側の確認がとれた場合、席を共にして考えをお互いに伝える。それはつまり、お願いを受けても「行きたくない」と伝えれば会わないことは可能だということだ。それによる罰則もない。手紙による、依頼者を通さない間接的なやりとりなので、断りづらさも減る。断ることは容易なのだ。
もし、裁判の手続き、学校の学級指導など、ルールに沿った流れがあれば、調書をとられ、証言をとられ、実刑を言い渡されるといったこともある。呼び出され、話を促され、和解を強要されるかもしれないなど、今後自分に起こることが想像できる。そして、決められた手続き内では、相手との直接交渉が意外と少ないのではないか。接触の機会が少ないことや、第三者による介入が強いため、両者は、それほどの痛みを感じることなく終わることもあるだろう。
一方、対話の会では、会の流れやルールの説明を受けても、実際にどのような場になるのか想像が難しいし、保証もない。被害者から一方的に「非難」を受け続けるかもしれないし、加害者側からの口先だけの謝罪を延々と聞かされるかもしれない。そうなる可能性も大いにあるし、真の謝罪がなされる保証もない。自分の意思で、ただただ苦痛を感じる場となってしまうかもしれない。
しかし、この方法で対話の会は成立し、それどころか拒否の態度をとる人は多くないという。このことにとても衝撃を受けた。強制でもなく、得るものの保証もなく、自ら傷つけた、傷つけられた者と場を共にし、あの時のことをもう一度振り返る。そんな場に「行ってもいい」という人がいること、そしてそんな人たちが決して少なくないことに、光を感じた。対話の会の存在と維持が、犯罪者の更生や被害者の自立とケアなど、司法福祉が夢物語、綺麗事ではないことを毅然と証明してくれているように思えた。
罪を憎んで人を憎まず、という言葉が浮かぶ。日本では対話の会のような存在がまだまだ少ないらしいが、今後そのような活動が活発に行われるようになれば、ある意味で司法福祉が着実に発展している証になるのではないだろうか。